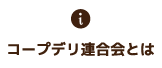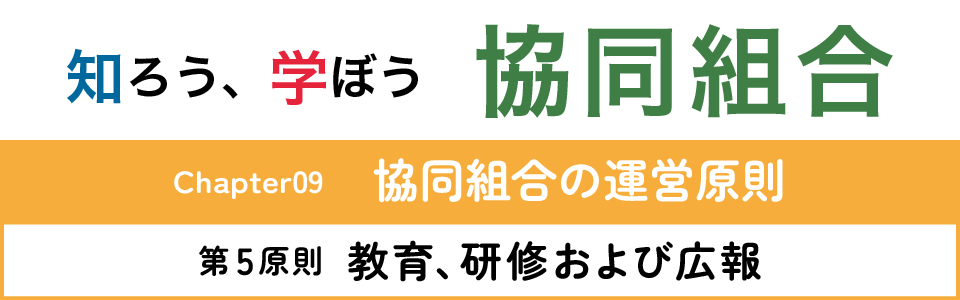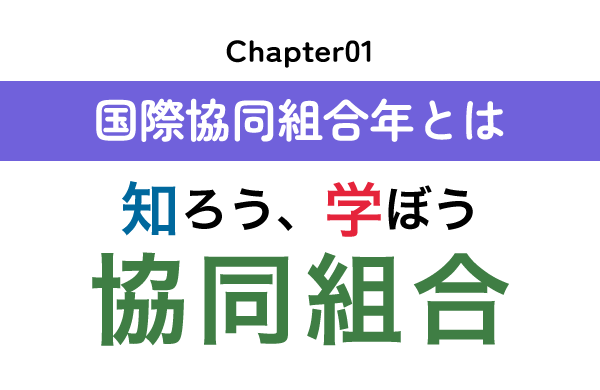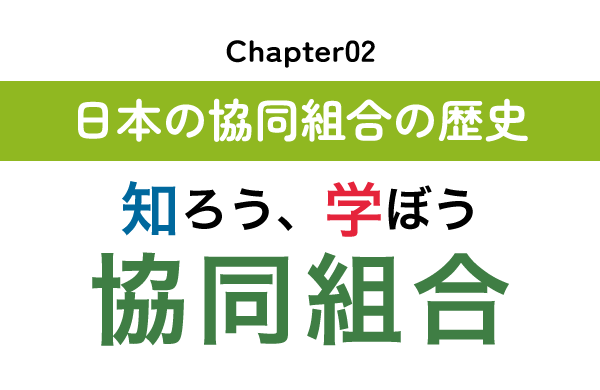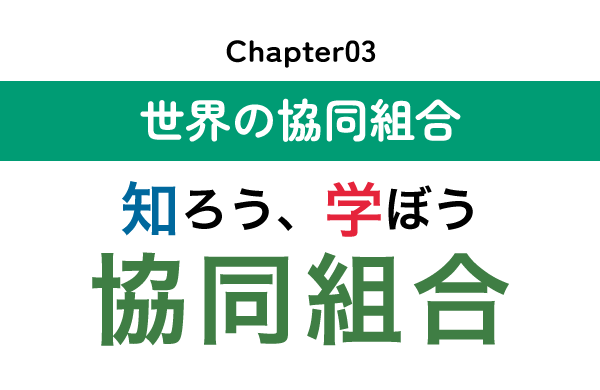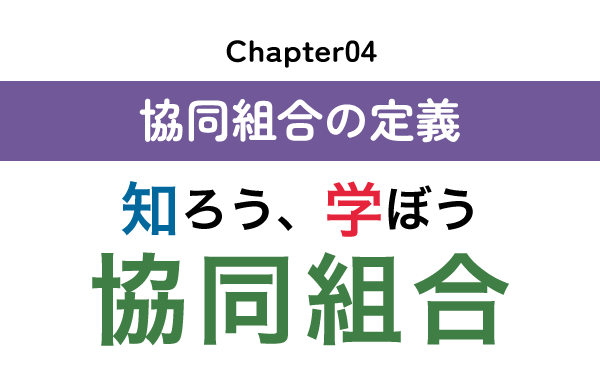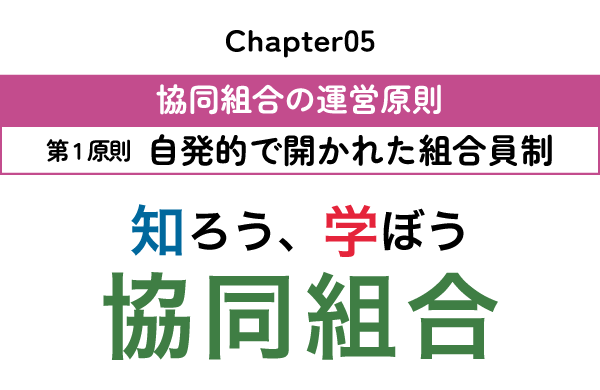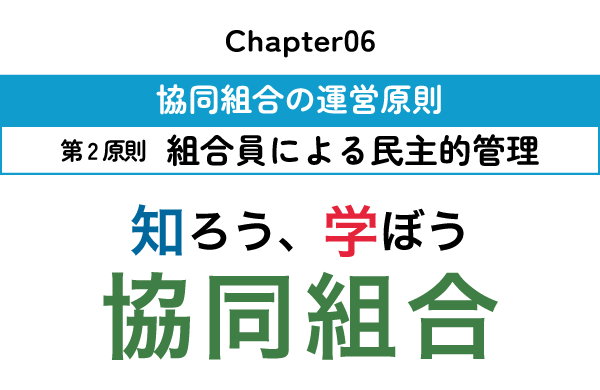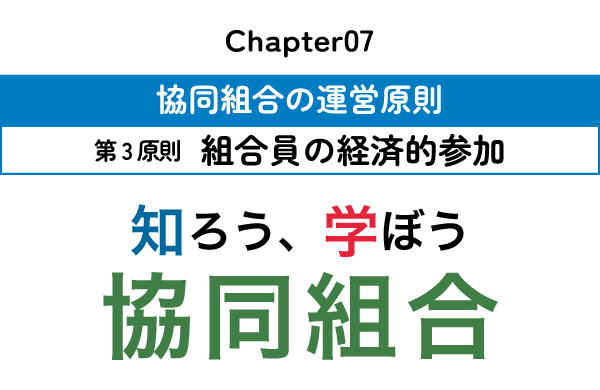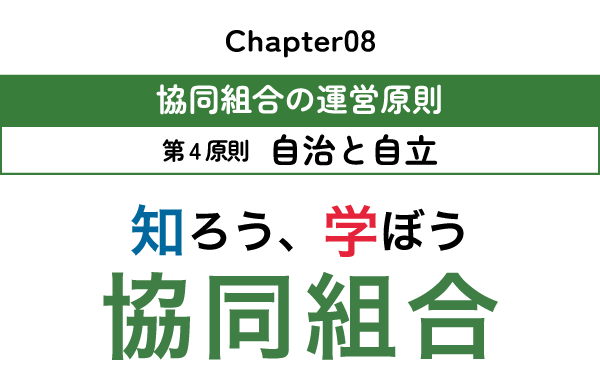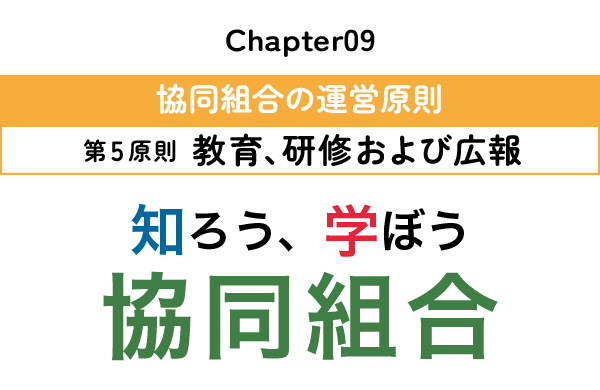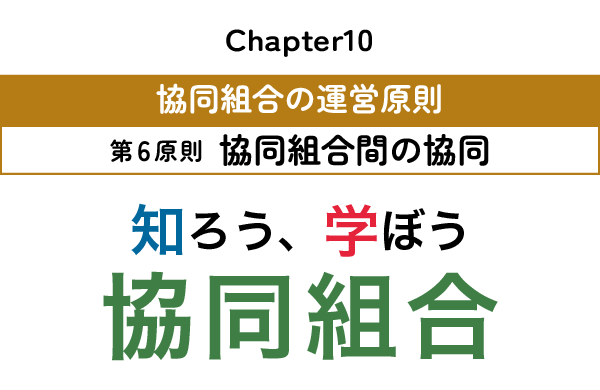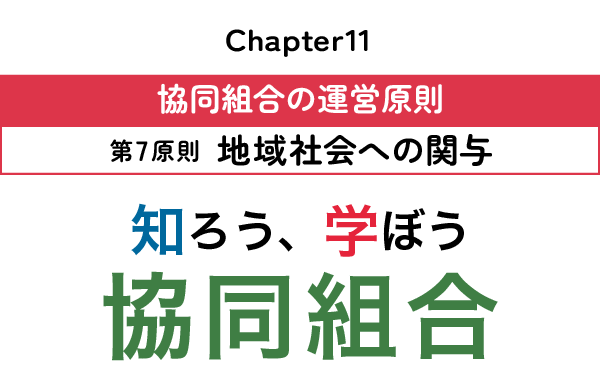協同組合は、世界中で100カ国以上にあり、その組合員の数は10億人を超えています。国際協同組合同盟(ICA)は、1995年に「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を発表しました。この声明では、協同組合の定義や大切な考え方、運営のための7つの原則が示されています。今回は第5原則を紹介します。
協同組合の役割
① 組合員や役職員に教育や研修を行い、協同組合の発展に貢献できるようにすること
② 一般の人々、特に若い人や意見を持つ人たちに協同組合の活動の重要性を広めること
ともに学びあう
協同組合は、組合員の共通のニーズや願いを実現するために協力して事業を行う組織です。組合員が、出資したり、事業を利用したり、運営に参加したりするためには、一人ひとりが事業の必要性を感じることが大切です。もし組合員が協同組合の活動の必要性や参加の大切さを忘れてしまうと、協同組合は成り立ちません。そのため、組合員への教育や研修はとても重要なのです。また、教育は講義だけでなく、日常の活動を通じて協同の必要性やその考え方を学ぶことも大切です。
もちろん、役職員への教育も重要です。役職員が協同組合の理念を理解することで、事業の成果が大きく変わります。役職員一人ひとりが専門的な知識や技術を身につけることで、組合員のニーズに応えられるようになります。
若い人やオピニオンリーダーへの発信を
第5原則は、協同組合が若い人や意見を持つ人たちに協同組合の活動の重要性を広めることの大切さも強調しています。組合員や役職員への教育・研修だけでなく、まだ協同組合に参加していない一般の人たちに協同の魅力を伝え、協同の輪を広げていくことが求められます。だからこそ、これからの社会を担う若者や意見を持つ人たちへの広報活動が重要なのです。
そのため協同組合は、大学での協同組合に関する講座を増やしたり、若い人や意見を持つ人たちに向けた情報発信も大切にしています。
日本の生協の組合員のうち
20代・30代の構成比は9.3%

「2024年度全国生協組合員意識調査」によると、組合員の平均年齢は60.5歳で、そのうち20代・30代の構成比は9.3%です。
調査開始以降初めて、組合員の平均年齢は60代を超え、40代以下の構成比が減少する傾向が続いています。
生協加入率は、年度によってばらつきがありますが、2015年度以前は20代・30代の加入率が10%を超える年度があるのに対し、2018年度以降は10%未満が続いています。
若年層の生協加入率は極端に減少しているわけではないものの、減少傾向にあると考えられる状況です。
出典:『2024年度全国生協組合員意識調査』(2024年11月:日本生活協同組合連合会)