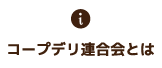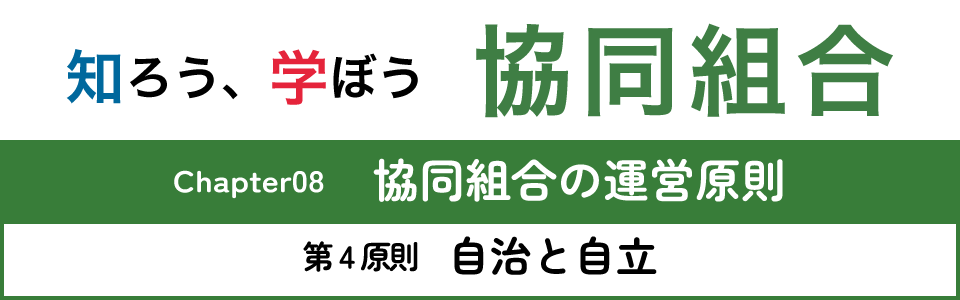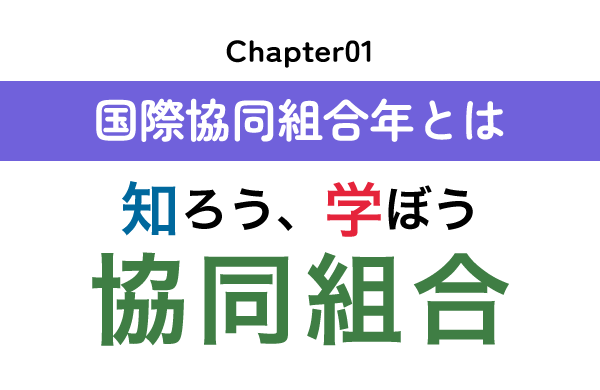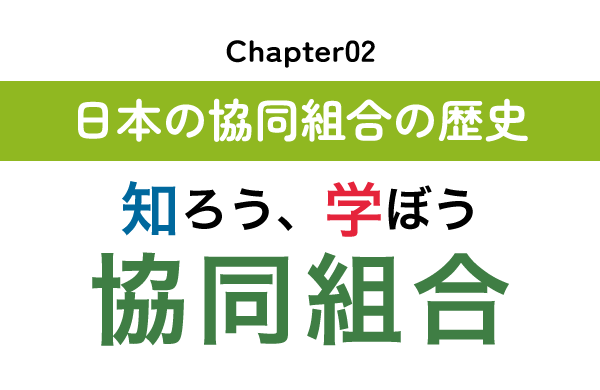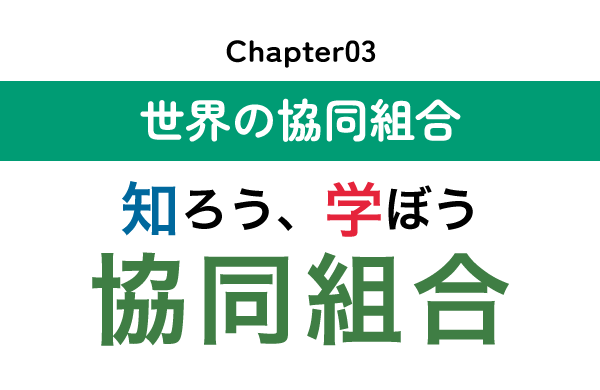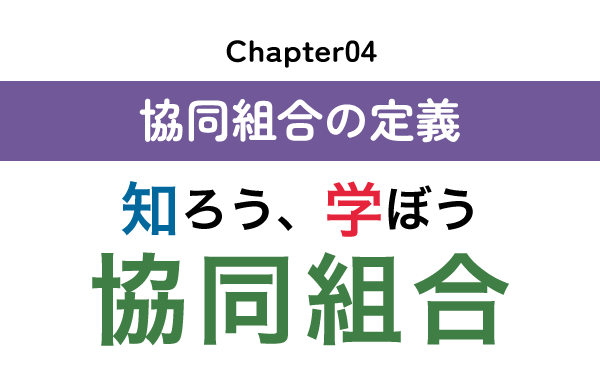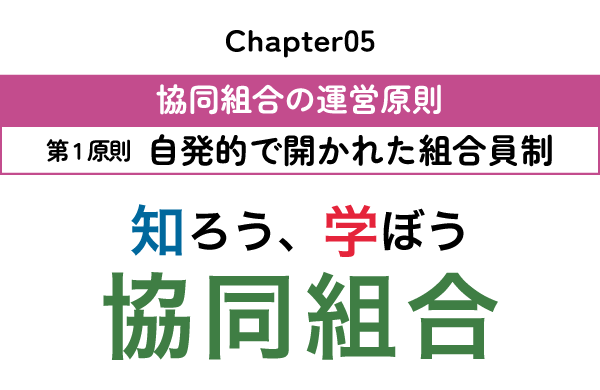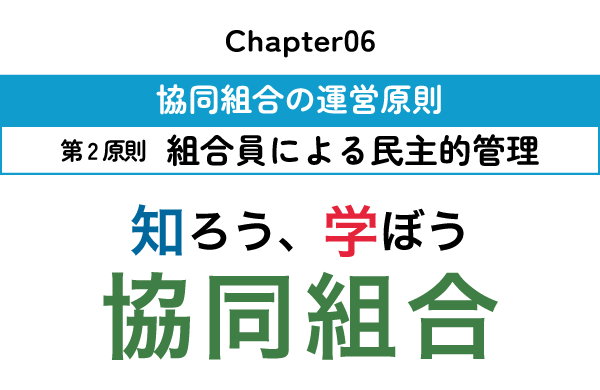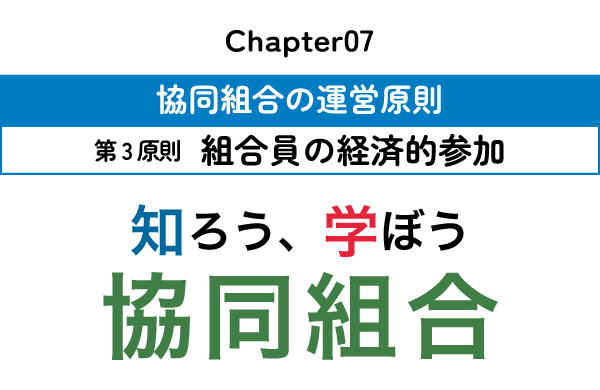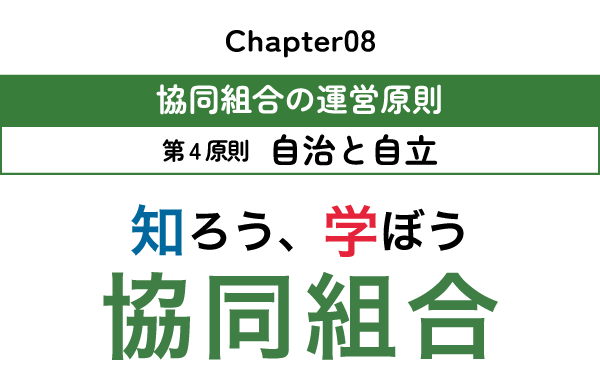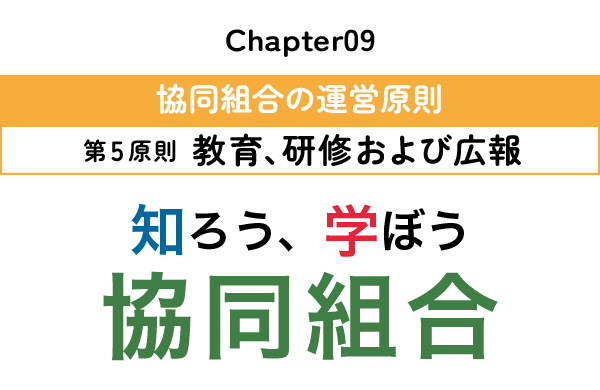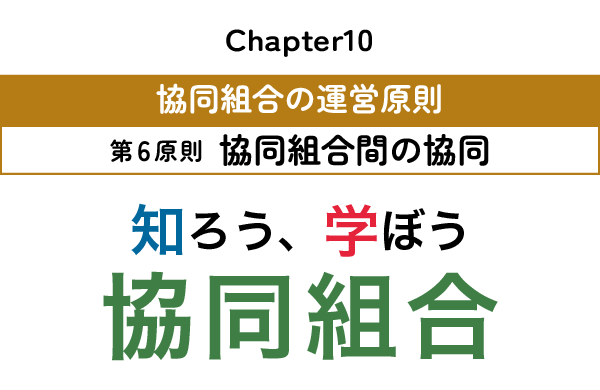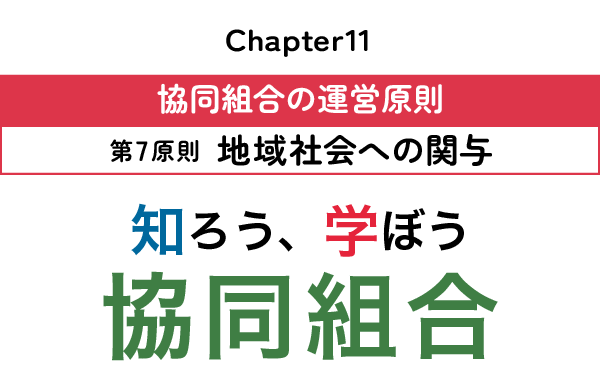協同組合は、世界中で100カ国以上にあり、その組合員の数は10億人を超えています。国際協同組合同盟(ICA)は、1995年に「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を発表しました。この声明では、協同組合の定義や大切な考え方、運営のための7つの原則が示されています。今回は「自治」と「自立」に関する重要な指針である第4原則を紹介します。
政治的にも経済的にも自主・自立が基本
協同組合の商品やサービスを組合員が利用することで、組合員自身のくらしを良くしていくことが、私たちが協同組合をつくる目的です。この目的を達成するためには、組合員が自分たちのことを自分たちで決める「自治」が必要です。
協同組合の運営を、政府や外部企業に頼りすぎてしまうと、結果として「本当に必要なときに動けない」「自分たちの意見が言えない」といった問題が出てきます。
協同組合と政治との関わり
協同組合は社会を良くするための組織ですが、政治とどう付き合うかには注意が必要です。政治との関わりについて、2つのポイントを紹介します。
① 組合員それぞれの政治への考え方を尊重する
どの政党を応援するかは、一人ひとりの自由です。協同組合として、特定の政党に「賛成・反対」を強要してはいけません。
② 自由な発言と行動
組合員の意見がまとまった場合、政治や社会に向かって声をあげることもできます。協同の力でくらしや地域を良くしていくために、アクションを起こすことも大切です。
組合員の自覚と主体性
外部に頼りすぎてはいけないと言っても、物事が複雑化した現代では、外部との連携や協力がなければ協同組合の発展は難しくなっています。外部の協力を得る際は、頼りすぎず、自主性を保ちながら、組合員が「自分ごと」として活動に参加すること、さらに政府や企業に対して自分たちから働きかけることが必要です。なかなか難しいことですが、これを最終的に支えるのは、組合員一人ひとりの主体性と、それを後押しする組織的な仕組み(参画の確保)なのです。
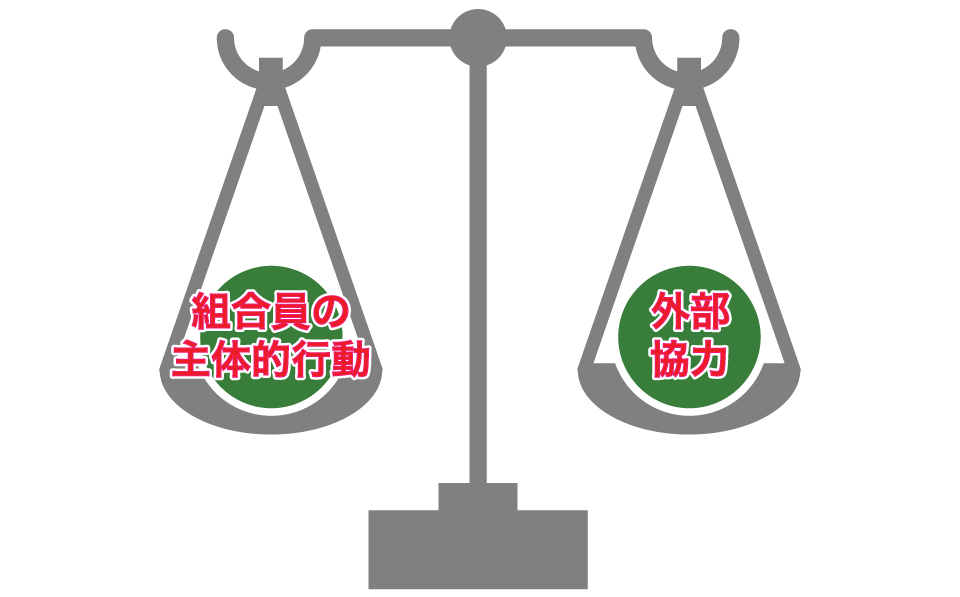
外部協力だけでなく、組合員の主体的行動こそが協同組合を支える原動力です
協同組合を通じて出荷・販売される
国内の農林水産物の割合51.6%

農協や漁協などの協同組合の販売事業は、組合員が生産した生産物の販売(卸売市場への出荷など)を、組合員に代わって協同組合が行う事業であり、主に農林水産業で実施されています。
2022年度の国内の農林水産物販売取扱高11兆1,568億円に対する協同組合の販売取扱高の比率は、51.6%(※)。国内で生産された農林水産物のうち、金額ベースで半分超が協同組合を通じて販売されていることになります。
※『2022年事業年度版協同組合統計表』(2025年3月:日本協同組合連携機構)