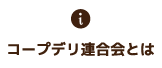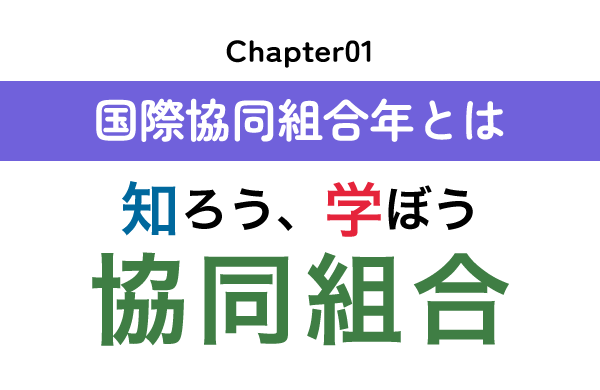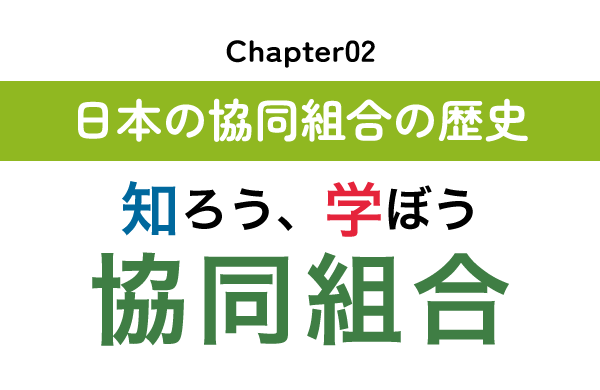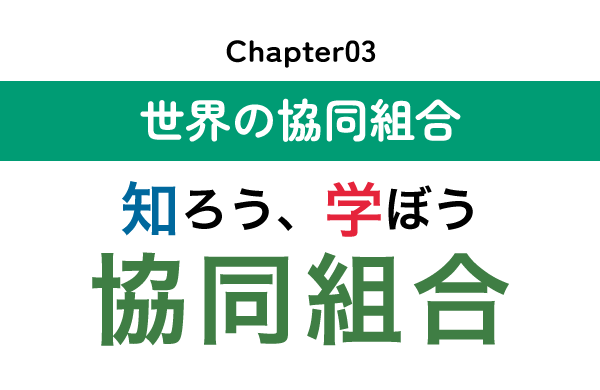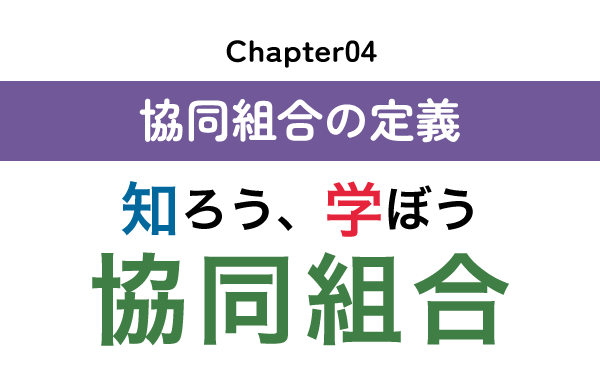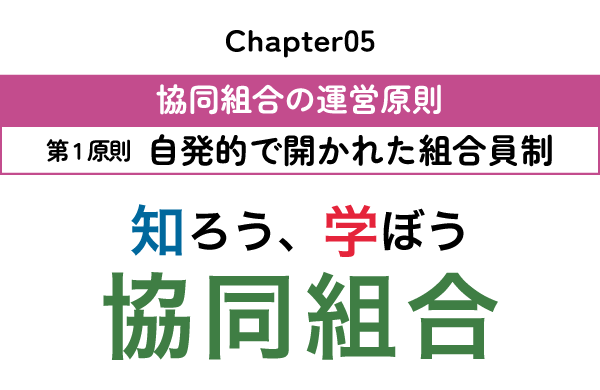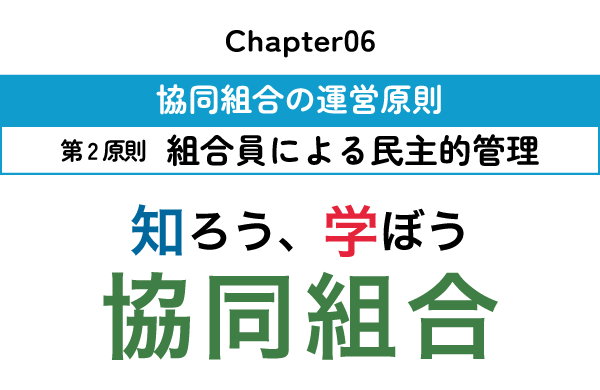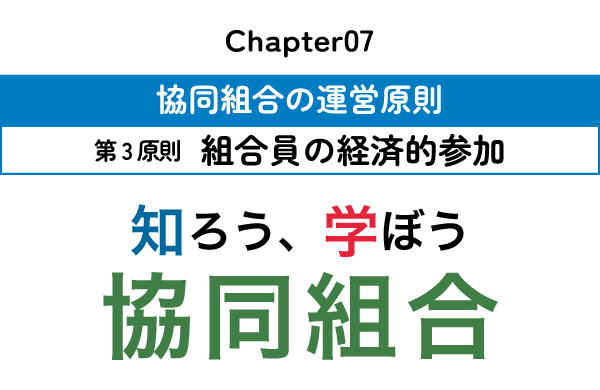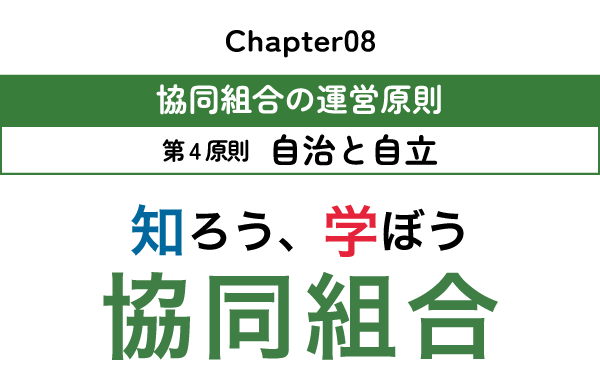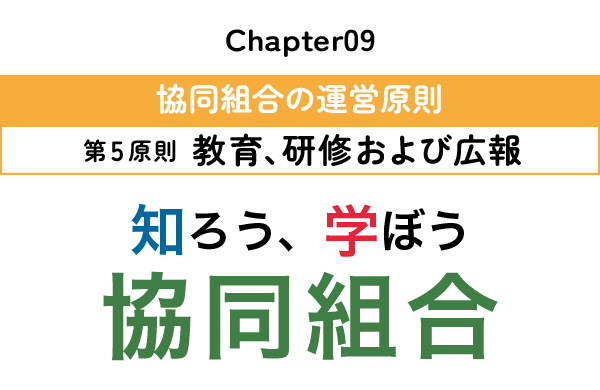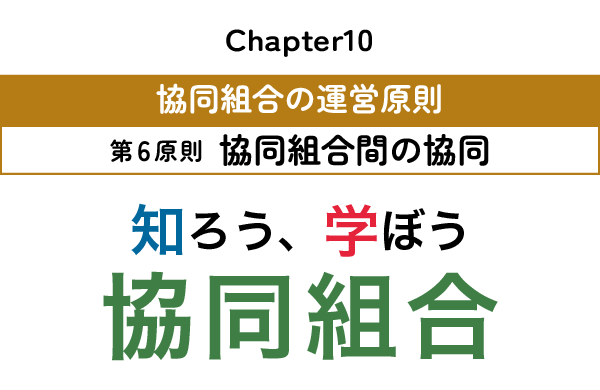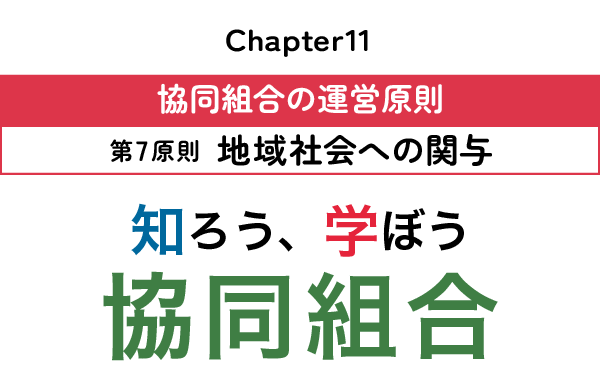協同組合の歴史は江戸時代から
協同組合は、人々が協力して助け合うことで、くらしが豊かになって、誰もが幸せになるために作られた組織です。協同組合はその時代に応じて、組合員や社会が抱える問題を解決するために活動してきました。今回は日本の協同組合の歴史を振り返ってみましょう。
江戸時代末期
江戸時代の農民思想家で、勤勉と自助を説いた二宮尊徳は、経済的に困っている人たちのために「五常講」という相互扶助や地域経済の発展を促進する信用組合のような仕組みを作りました。また、農民の生活向上を目指した江戸時代の思想家、大原幽学は「先祖株組合」を結成し、土地を出資してその収益で農民たちが助け合って生活できるようにしました。
大正時代
日本の協同組合運動の父と呼ばれる賀川豊彦は、貧しい人々を助けるために労働運動や農民運動、普通選挙運動などの社会改革運動を進めました。賀川が作った神戸購買組合(現在のコープこうべ)は、今の協同組合の始まりとなっています。
さまざまな協同組合
協同組合が全国に広がるきっかけとなったのは、1900年に成立した産業組合法です。その後、1947年には農協法など、さまざまな協同組合に関する法律が次々と作られ、最近では2022年に労働者協同組合法が施行されました。このように、さまざまな種類の協同組合がそれぞれの法律に基づいて活動しているのが日本の協同組合の特徴です。
日本の組合員数1億820万人

日本では、のべ約1億820万人が協同組合に参加しています(※1)。日本の協同組合への加入率は、個人で46.5%、世帯で51.4%とされています(※2)。
※1『2021年事業年度版協同組合統計表』(2024年3月:日本協同組合連携機構)。複数組合に加入の場合は組合員数を重複計上。
※2『協同組合に関する全国意識調査2022』(2023年3月:日本協同組合連携機構)