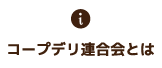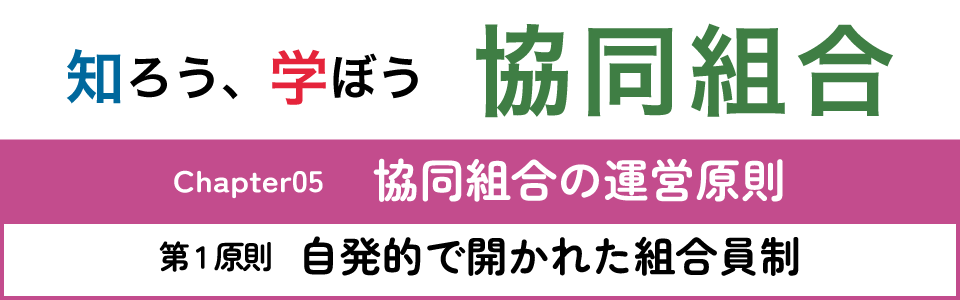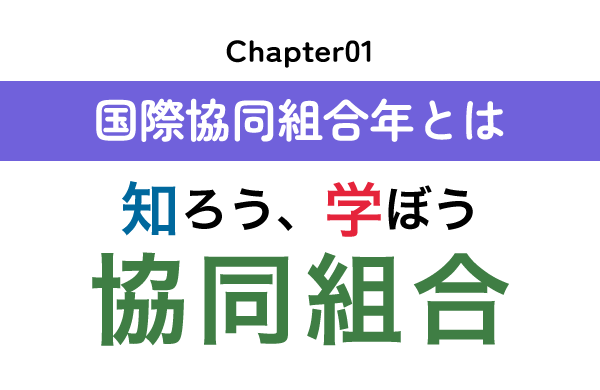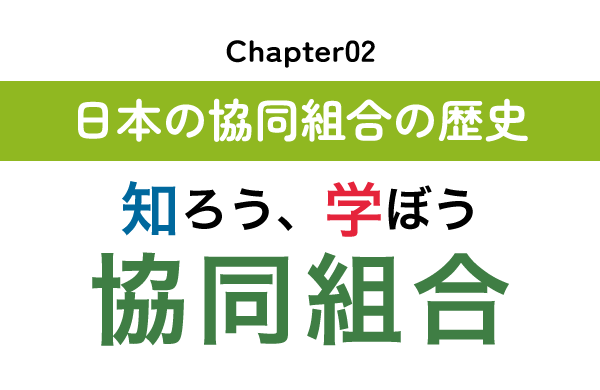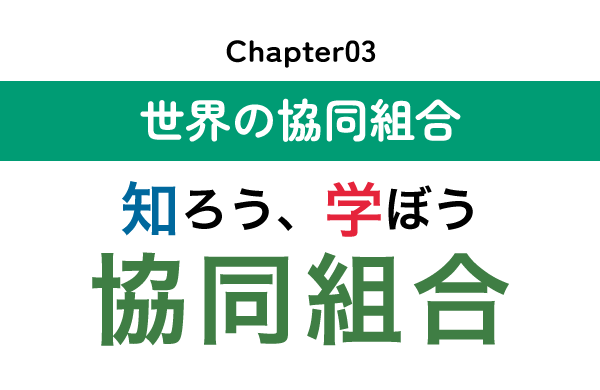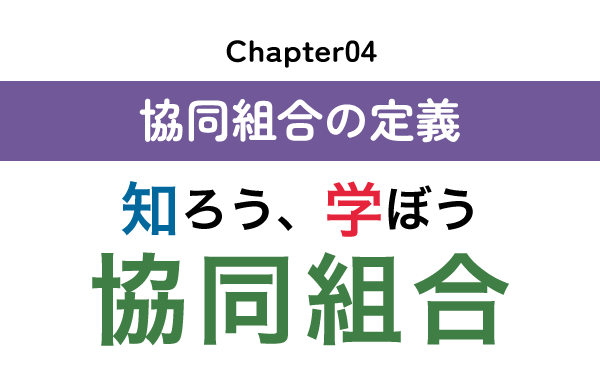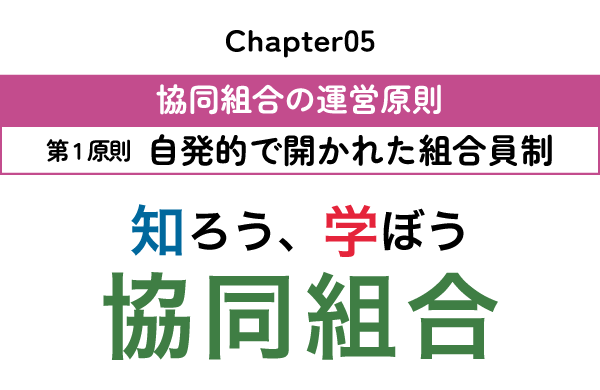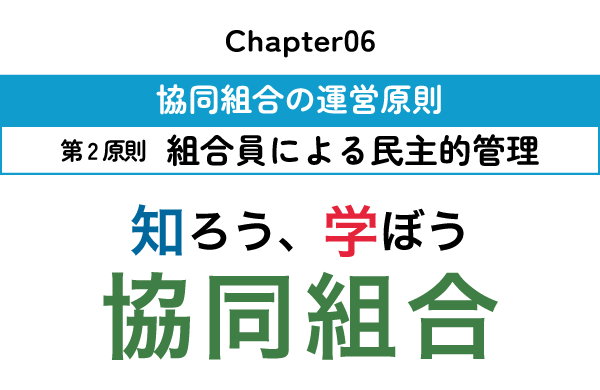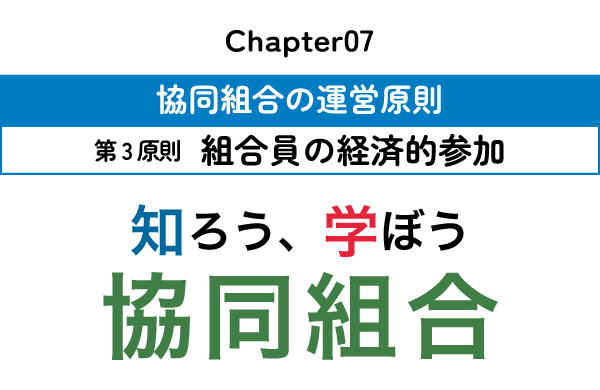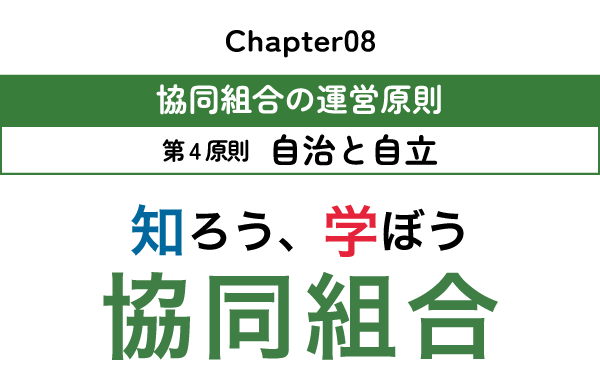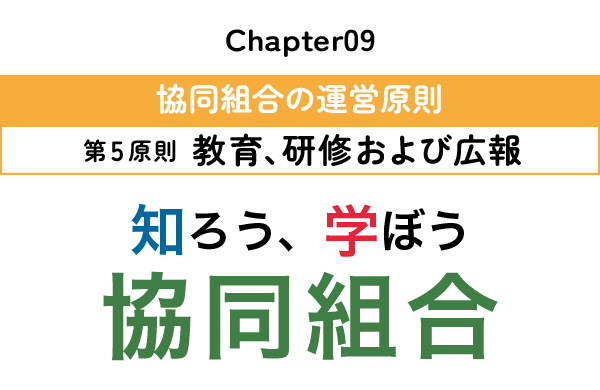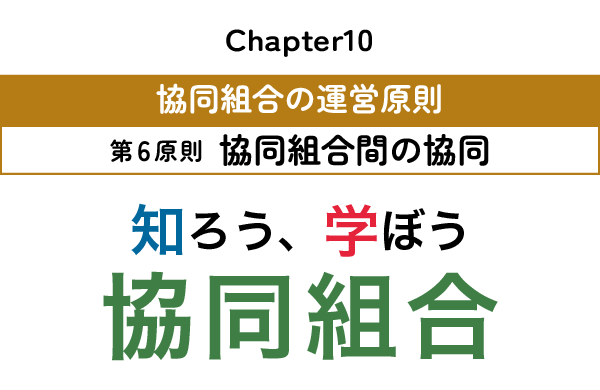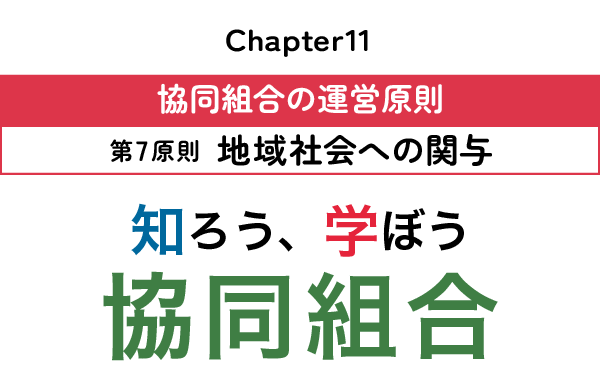協同組合は、世界中で100カ国以上にあり、その組合員の数は10億人を超えています。国際協同組合同盟(ICA)は、1995年に「協同組合のアイデンティティに関するICA声明」を発表しました。この声明では、協同組合の定義や大切な考え方、運営のための7つの原則が示されています。
協同組合の第1原則 3つのポイント
① 組合員制をとる
「組合員制」とは、協同組合がその組合員によって成り立っていることを意味します。ここでの「組合員」とは、経済的、社会的、文化的なニーズを満たすために、自発的に集まった人たちのことです。この原則では、どんな人が組合員になれるかが説明されています。
② 自らの意思で
「自発的」とは、協同組合を作ったり、加入したりするのは、その人自身の意思であるべきだということです。つまり、誰かに強制されることはなく、自分が加入したいと思ったときに参加できます。これは、国によっては政府が人々に協同組合への加入を強制することがあったため、重要なポイントです。
③ 誰でも加入
「開かれた」とは、基本的に希望する人は誰でも協同組合に加入できるということです。具体的には、性別、社会的な背景、人種、宗教、政治的な立場などによる差別をしてはいけないとされています。ただし、加入には2つの条件があります。
条件1:協同組合のサービスを利用できること
例えば、農業者が農協を作る場合、その農協のサービスを利用できる人だけが加入できます。
条件2:組合員としての義務と責任を受け入れる意思があること
加入を希望する人は、議決権を使ったり、会議に参加したり、協同組合のサービスを利用したり、出資金を出すなどの、義務と責任を受け入れる意思を持つことが必要です。
また、第1原則の「開かれた」という言葉には、協同組合が得られる利益を特定の人だけでなく、より多くの人に広げていこうという考えがあります。
組合員が利用できる
協同組合の施設数
約3万4,000か所

日本国内に組合員が利用できる施設は、3万4,000か所(※)あります。具体的には、スーパーマーケットや農協の直売所、漁協の販売所、協同組合が運営する病院や介護施設があり、全国の生協やさまざまな種類の協同組合が提供する施設を含んでいます。
※『2021年事業年度版協同組合統計表』(2024年3月:日本協同組合連携機構)